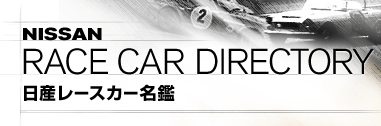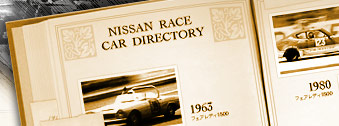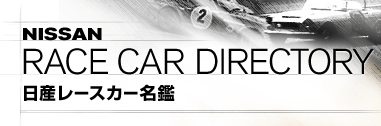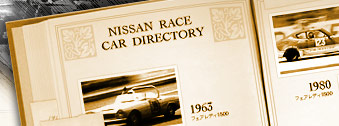|
|
|
 |
 
 |
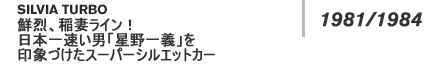 |

 |
1980年代初頭に行われたスーパーシルエットレースの熱狂は、前回お伝えしたとおり。今回は、その人気の中心だった3台の日産ターボ軍団のうちシルビアターボにフォーカスする。
日産がFIAのグループ5規定によるスーパーシルエットレースに参戦を始めたのは、79年から。初参戦のこの年は、柳田春人のドライブによるバイオレットターボ(A10)で1台がエントリーしている。翌80年も同様に、柳田のバイオレットターボ1台が参戦し、見事にシリーズチャンピオンを獲得している。
81年、日産はバイオレットターボに代わり、シルビアターボとガゼールターボの2台の兄弟車をエントリーさせた。白いボディに黄色のラインのマシンが、星野一義のシルビアターボ。シルバーベースのボディカラーのマシンが、柳田春人のガゼールターボだ。この2台は、基本的には全く同一のマシンと考えてよい。しかし、右の写真をよくみると、手前のガゼールターボには大きなリアウイングが装着されている。一方、星野のシルビアターボにはリアウイングがない。その代わりにフロントのスポイラーに垂直のフィンが装着されている。当時のエンジニア、岡寛(現レース技術部)は、「エアロパーツの改善を狙ったのだが、実際には各チームで、それぞれのノウハウをベースに試行錯誤を繰り返していた」と語っている。つまり、この2台の差は各チームの考え方の違いなのだった。こうした細かい試行錯誤が、毎戦のように繰り返されたことも、このレースの魅力のひとつであったことは間違いない。
実は、81年仕様のスーパーシルエットカーは、まだパイプフレームシャシーではない。初期のGTカーのように、生産車ボディを大きく改造していたのだ。この年、シルビアは星野の手でデビューウィン。その後、柳田のガゼールが2勝をあげ、迫力のエアロボディによるスーパーシルエット伝説がスタートしたのだった。
82年、日産のスーパーシルエットカーは3台になる。星野のシルビアターボに加え、柳田はブルーバードターボに変更、そして新たに長谷見昌弘のスカイラインターボが加わった。この3台の日産ターボ軍団の登場によって、スーパーシルエットカーレースの人気は、ますます加速していった。
マシンも大きく変更され、本格的なパイプフレームシャシーとなった。岡によれば、「スーパーシルエットは、フロントに今では考えられないくらい
巨大なインタークーラーを装着していた。結局、ラジエターの置き場がなくなり、サイドラジエター方式にしたんだ。当時は、サイドラジエターのマシンなんて、世界的にみてもなかったから、今思えば、かなり先進的なマシンを造っていたんだよ」と当時を振り返る。しかし、パイプフレームシャシーの剛性は低く、各チームはアンダーステアに悩まされることになる。
83年、日産チームは昨年同様の3台体制でレースに臨んでいる。この年のシーズン中盤、市販車のシルビアがS110型からS12型にフルモデルチェンジした。これに伴い、星野のシルビアターボも、角目4灯のS110型から、リトラクタブルライトのS12型をイメージしたボディカウルに変更された。そしてこの年をもって、富士GCシリーズのスーパーシルエットカーレースは終了。
84年、菅生、西日本、筑波の各サーキットで一戦ずつ行われたスーパーシルエットカーレースに、星野のドライブでシルビアもエントリーしているが、これが最後の年となった。
シルビアターボは、日産ターボ軍団のなかで最も長くスーパーシルエットレースに参戦したマシンで、81年から84年の4年にわたるレース活動において、ドライバー、カラーリングともに変更されることはなかった。白いボディに黄色の稲妻ストライプは、そのままドライバーである星野一義をイメージさせ、人々に鮮烈な印象を植え付けた。そして、星野もこの時代から、日本一速い男への道を走り出したのだった。
|
  |