|
|
 |

レーシングカーが「走って、曲がって、止まる」ために絶対に必要なものとしてタイヤがあります。これは自動車メーカーが作ることのできない重要なパーツのひとつです。
タイヤは元々自転車用のものとして19世紀のイギリスで発明されましたが、タイヤ全体がゴム製でした。やがて中に空気を入れ乗り心地が向上。19世紀後半に発明された自動車にも採用されました。タイヤの基本的な材料はゴムですが、耐久性を持たせるために金属のワイヤを入れたり、
化学物質を加えるなど、その技術はゴム/タイヤメーカーのノウハウとなっています。
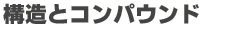
構造的には、空気の圧力を支えるΩ状のカーカス、そして接地面のベースとなるベルトがあり、その周りを黒いゴムが覆っています。さらに黒いゴムの表面、つまり実際に路面と接触する面には、構造体とは別のゴムがコーティングされた状態になっています。この部分のことを「コンパウンド」と呼んでいます。コンパウンドには柔らかいもの(ソフト)、硬いもの(ハード)、またはその中間のもの(ミディアム)など、その時の路面温度に応じて、いくつかの種類が用意されています。また寒いシーズンにはミディアムとソフトの中間の「ミディアムソフト」と呼ばれるものや、ソフトをさらに柔らかくした「スーパーソフト」と呼ばれるものが存在する場合もあります。しかしNISMOが使用するブリヂストン製タイヤのコンパウンドは、基本的にソフト、ハードの2種類で、まれにミディアムを用意します。ソフトは柔らかくてグリップがいいので速いタイムが出ますが、磨耗も多く長く走れません。ハードは硬くて磨耗が少ないので長く走れますが、速いタイムは出にくいという性格を持っています。ミディアムはその中間で、コンディションが合えばタイムがそこそこ出てそこそこ走れますが、逆にコンディションが合わずタイムも出ず長く走れない場合もあります。なおNISMOが使用するブリヂストン製タイヤは、レースに持ち込む際には1種類の構造です(他タイヤメーカーや他車では2種類を持ち込む場合もあるようです)。
さて、市販されるフェアレディZのタイヤサイズは、前が225/45 R18(タイヤ幅=225mm、扁平率=45%、ホイール径=18インチ)、後ろが245/45 R18ですが、SUPER GTのGT500Zは、前後とも330/40 R18と10cm近く広いことが分かります。これは500psを超えるパワーを路面に伝えるため、そして300km/hに近いトップスピードから確実にブレーキをかけるためです。でもあまり広げすぎると、今度は直線区間では逆に抵抗になってトップスピードが落ちてしまいます。現在のタイヤサイズはSUPER GTの車両規定に則ったベストサイズということができるでしょう。
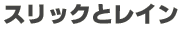
SUPER GTレース用のタイヤは、ドライコンディション(乾いた路面)を走る溝のない「スリックタイヤ」と、ウェットコンディション(雨などで濡れた路面)を走る「レインタイヤ」に分けることができます。
スリックタイヤには、普段乗用車で目にするような溝がありません。乗用車用タイヤの溝は、タイヤと路面の間にある水を排除するためのもの。ですからドライコンディションでは接地面積が多いほどグリップ力が増す、スリックタイヤを使用します。
レインタイヤは、路面が濡れている場合に使用します。またレインタイヤには2種類あり溝の深さが異なります。路面がちょっと濡れている場合に使用するのが、溝が浅くて少ない「浅溝」で、水の量が多い場合に使用するのが、溝が深くて多く排水性能に優れた「ノーマル(深溝)」です。この2種類の使い分けですが、これは路面の水の量で判断します。浅溝タイヤでハイドロプレーニング現象(路面とタイヤの間に水の膜ができて、水の上を滑るような状態。マシンコントロールができず危険)が起きたら、即、深溝に交換します。深溝から浅溝への交換は、ラップタイムを参考にします。なお、レインタイヤにもコンパウンドはソフトとハードの2種類が存在します。
このように1つのレースには最低でもスリックがコンパウンド違いで2種類、レインが溝の深さ違いで2種類、さらにコンパウンド違いで2種類の計4種類、合計6種類のタイヤの準備が必要です。またコンディションによっては、決勝レースで同じコンパウンドを2セット必要な場合も多く、どのタイヤを2セット、もしくは3セット準備するか悩むところです。
実際、レースウィークでは何セットのタイヤを使用するのでしょうか? 規定では、金曜日の練習走行では3セットのみが使用できます。また予選前の時点で、使用されるタイヤは3セットに制限されマーキングが行われます。このマーキングがされていないタイヤを履くとルール違反となります。マーキングは、予選専用のタイヤを投入したりして経費の高騰を防ぐために実施されています。予選に使用するのは、このマーキングされた3セットのうちの2セットです。基本的に予選1回目に1セットを使用して、スーパーラップでもう1セットを使用します。日曜日朝のフリー走行も、それまでの2セットの中古タイヤを使用します。そして決勝レースに使用するのはマーキングされた残りの1セットです。ただし雨が降って「ウェット宣言」が出されると、使用するタイヤは自由となります。
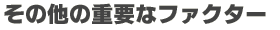
タイヤで重要なファクターは、コンパウンド以外にもあります。それは内圧です。つまりタイヤ内部の空気圧のこと。ゴムまりを想像してみれば分かりますが、内圧が高ければよく弾み、逆に低いと跳ねません。良く弾んでも路面をグリップしないと意味がありません。さらにタイヤは走れば走るほど摩擦熱で空気の温度が上がり、内圧は高くなっていきます。この内圧の設定はこれまでのレースデータを基に決めています。また内圧のチェックや調整は、クルマがピットインする際には必ず行っています。
さて、タイヤを使用する場合には、よく「皮むき」という言葉が使われます。これはタイヤの表面を発熱させてベストグリップ状態の手前まで持っていくことです。発熱させるためには、フロントタイヤの場合はブレーキングで前に荷重をかけて行い、リアタイヤの場合はホイールスピンさせて行います。
ウェービングといってハンドルを左右に切って蛇行しながら温める場合もあります。
皮むきに要するのは、夏場で1/2〜1周、冬場で2〜3周。ですから予選のスーパーラップを見ていると、特にコースインの周でタイヤを温める様子が分かります。また決勝レースのフォーメーションラップでもウェービングが見られます。
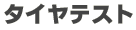
さて、NISMOでは年間に何回かタイヤテストを行っています。NISMO独自に行うこともありますし、他メーカーと合同で行うこともあります。さらにGT-Aの合同テストも行われます。このタイヤテストでは何が行われているのでしょうか?
まず、タイヤのチェックとそのタイヤに合わせたセッティングを決めることが大事です。さらにレースで実際に使用するタイヤのコンパウンドをここで決めます。レースウィークに使用するタイヤのコンパウンドはレースの約1か月前にオーダーをしなければなりません。したがってレース前のテストはレースウィークの1か月以上前に行われることが多いのです。この1か月のタイムラグが結構くせ者で、気温が30℃を超えるような暑い時期に秋用のタイヤテストを行ったりしますし、1か月先の天気や気温をぴたりと当てることは困難ですから、テストで選んだコンパウンドが“外れる”こともあります。
またテストでタイヤ選択とセッティングがおおよそ決まったら、“ロング”と呼ばれるロングランテストを行います。走行距離は決勝レースを想定して行います。このロングでは、タイヤの磨耗や満タン/空タンク時のラップタイムの変化など、こまかいシミュレーションを行っているのです。タイヤテストで比較的早い時期にロングを行っているチームほどセッティングが決まっている証拠です。

レース終了後のタイヤの検討はすぐにタイヤメーカーと共に行われ、次のタイヤテストのための準備に取り掛かります。またタイヤだけでなくホイールのチェックも重要です。レースやテストに出かける前、また帰ってきてから、NISMOではメカニック全員で1日をかけてホイールに傷が入っていないか、クラック(亀裂、ひび割れ)が入っていないか、リムや内側が凹んだり削られていないかをチェックしています。
なお、ブリヂストン製のタイヤでも、Z用とスープラ用、NSX用のタイヤは全く一緒ではありません。NSX用はフロントタイヤの幅が異なりますし、Z用とスープラ用はタイヤの構造が微妙に異なっているようです。これは各車両の特性に合わせたためです。
またNISMOでは基本的に1セット4本のタイヤは同じものを使っています。他のカテゴリーや他チームでは、コースやコンディションによってはフロントの2本や、左の2本だけを柔らかくしたりしていますが、Zはマシンバランスも良く、あまり気をかける必要がないようです。
さらにNISMOでは、レース中のピットイン時には必ずタイヤ交換を行っています。これはタイヤを交換せずピットインの時間ロスを稼ぐより、フレッシュなタイヤでリカバリーする方が速くかつ安心ですし、わざわざリスクを冒す必要はないという考えのためなのです。
|
 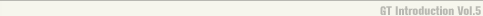  |
 |
|