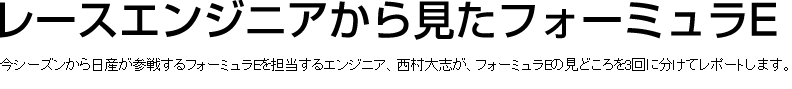
レースの見どころは?
レーススタートからゴールまで45分(+1ラップ)と、F1やSUPER GTに比べると短いですが、その中でも順位の入れ替わりがあり、最後まで目が離せないレースです。また、FanBoostは、TwitterなどのSNSを通じた人気投票で最も多くの票を集めたドライバー5人に、約5秒間の50kwパワーアップが与えられますが、これはレース開始から約15分後に決定します。よって、予選結果、さらにはレーススタート後に票を動かすことができます。このFanBoostは、レース後半で使うことがルールで定められていますので、どのタイミングで使うかは注目です。もう一つのパワーアップ機能であるAttack Mode。これは規則上、必ず使用しなければなりません。しかし、通常の走行ラインからは外れた場所にAttack Modeを有効にするゾーンが設置される場合があるため、そのゾーンをうまく通過しないと後続車に追い抜かれてしまうリスクがあります。追い抜かれた後に、+25kwのパワーで追い抜ける保障はありませんので、Attack Modeを使うタイミングも戦略の一つです。


電気自動車ですので、全車のバッテリー残量をTV映像で確認することができます。通常イメージするレース走行は、コーナー手前のぎりぎりまでアクセル全開で我慢する、という操作かと思いますが、FEではそのような走り方をすると、45分間を走り続けることができません。つまり、ラップタイムに貢献できる領域でエネルギーを使い、ラップタイムへの貢献度合いの低い領域ではエネルギーを抑制するという走り方、つまり、エネルギーマネージメントが必要になります。TV映像で聞こえるモーターの音を聞いて頂ければ、直線を走っている時のモーター音(=高周波のキーンという音)が、ブレーキ開始より手前で音色が変わることが分かります。同時に映像にあるバッテリー出力を見て頂ければ、ゼロkw付近になっているかと思います。これはリフトオフという操作で、アクセルOFFによってエネルギー消費を抑えています。でも、ドライバーの気持ちになってみれば、後続車が迫っている時にアクセル戻したくないですよね?しかし、戻さないと最後まで走りきれない・・・。このドライバー心理を考えながら見て頂くのも一つかと思います。ちなみに、このアクセルOFFのタイミングは、ドライバーとピット内のエンジニア、車載ソフトウェアが協力しながら1周の消費エネルギーが最適になるように演算し、走行しています。アクセル以外にも、ブレーキング時にはモーターが発電機の役割を果たす回生ブレーキ機能が搭載されており、タイヤ限界域で効率良くエネルギーを回収するための、ブレーキの使い方も重要となります。それらエネルギーマネージメントの結果、レース終盤でエネルギーが多く残っているチームは、エネルギーの少ないチームよりアクセルを踏み続けることができるので、最後に順位が逆転する可能性があります。そういった視点で見て頂けると、最後までレースから目が離せなくなります。

FEレースの難しさは?
FP1,2(=練習走行)からレースまで1日にまとまった短時間イベントであることと、市街地で様々な路面環境を走ることが、このFEの難しさだと思います。ローマは勾配が多いのが特徴ですし、パリは石畳路の上を走ります。また、三亜(中国)は今シーズン初めてのサーキットで事前情報が限られています。そんな中で、FP(=練習走行)、予選、レースと数十分、数時間おきにイベントが進むため、最適なセッティングを探し出す作業は非常に難しいです。ソフトウェア開発においても、環境条件に柔軟に対応でき、取得データの分析からデータ設定までを、効率的に、分かりやすく処理できるプログラムが求められます。

日産の特徴、競争力は?





