日産は23年前にパリ・ダカールラリーが始まって以来、一貫して参加しているメーカーの一つである。2001年の目標は、総合トップ3に入ること。
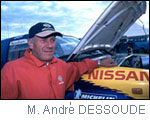 ノルマンディーにある日産ディーラー、アンドレ・ドスードが標準車に近い日産パトロールでパリ・ダカールラリー出場を決めた1983年が、ダカールラリーやFIAワールドカップ、ワールドラリーレイド選手権での日産車の活躍のスタートとなった。地味なスタートだったが、2001年のパリ・ダカールラリーが元日にパリから始まる今では、日産モータースポーツチームのテラノはベテラン参加者を脅かす存在となった。
ノルマンディーにある日産ディーラー、アンドレ・ドスードが標準車に近い日産パトロールでパリ・ダカールラリー出場を決めた1983年が、ダカールラリーやFIAワールドカップ、ワールドラリーレイド選手権での日産車の活躍のスタートとなった。地味なスタートだったが、2001年のパリ・ダカールラリーが元日にパリから始まる今では、日産モータースポーツチームのテラノはベテラン参加者を脅かす存在となった。
グループBラリーカー全盛時代のモノコックとスペースフレームのラリーカーは、公道で見る実際の車とは似ても似つかないものだった。日産は改造市販車でのT1、T2クラスへの参戦を貫いた。そのため、日産は華々しい総合優勝を犠牲にすることになったが、長距離ラリー界において、おそらくもっとも一貫し、信頼のおける参加者とみなされることとなった。
1983年以来、日産のクロスカントリー車両はクラスカテゴリー、ステージでの勝利、そしてマラソンタイトルを獲得してきた。アンドレ・ドスードとジャンピエール・リシャールは1984年と1985年にダカールのディーゼルクラスで優勝し、1988年には日産はマラソンクラスでのフロントランナーの地位を確立し、88年には2位を、翌年には優勝を果たした。ジャン・ブーシェと今年ニッサンチームとして出場しているジェローム・リビエールは91年のパリ・トリポリ・ダカールラリーのT1クラスで優勝している。
90年代を通して、日産車は信頼性を確固たる物とし、フランス人のティエリー・ドゥラベルニュを初めとするドライバーたちがクラスやセクションの表彰を多数獲得し、日産はコンストラクターズカテゴリーにおいて成功を収めた。もっとも困難で価値あるT1クラスでの勝利は、1992年のパリ・ケープタウンラリーでのディーゼルカテゴリー優勝だった。95年のグラナダ・ダカールラリーでは、パトロールがT1セクションで1位を、改造市販車のT2カテゴリーで総合3位・4位・5位を獲得し、すばらしい結果を残した。
 競技を統治するFIAが規則変更を行い、パワフルな4駆のプロトタイプ車を除外した結果、日産や三菱といったメーカーが上位を占める道が開かれた。日産はじわじわと進歩し、クラスでの上位独占から一目置かれる競技者へとなっており、1997年にはT2に参加するデュアルト・ゲデスとジャッキー・デュボワが、ニジェールのオクランとマリのキダールの間、537キロ地点でのステージを制覇した。スペインのサルバドール・セルヴィアは総合6位、フランス人元F1ドライバーのフィリプ・アリオも活躍を見せた。99年にはダカールラリーを何度も制したステファン・ペテランセルとティエリー・ドラベルニュがそれぞれ7位、8位に入賞したのだった。
競技を統治するFIAが規則変更を行い、パワフルな4駆のプロトタイプ車を除外した結果、日産や三菱といったメーカーが上位を占める道が開かれた。日産はじわじわと進歩し、クラスでの上位独占から一目置かれる競技者へとなっており、1997年にはT2に参加するデュアルト・ゲデスとジャッキー・デュボワが、ニジェールのオクランとマリのキダールの間、537キロ地点でのステージを制覇した。スペインのサルバドール・セルヴィアは総合6位、フランス人元F1ドライバーのフィリプ・アリオも活躍を見せた。99年にはダカールラリーを何度も制したステファン・ペテランセルとティエリー・ドラベルニュがそれぞれ7位、8位に入賞したのだった。
2000年には日産は3台体制でパリ・ダカール・カイロラリーに出場した。日産は、ドスードが作るV6のテラノに総合優勝の可能性がある、と信じていた。ドスードチームはダカール前にエジプトで繰り返しテストを行っており、3人のドライバーは序盤のほとんどのセッションでトップ10に入っていた。グレゴワール・デメビウスとドラベルニュはすばらしいステージタイムを出していた。しかし、デメビウスはリビアでの事故でリタイアし、チームメイトのフィリプ・ワンベルニュもエンジントラブルとなってしまった。ドラベルニュには運が味方し、事故で遅れたものの総合8位でゴールし、新型テラノにダカール初成功をもたらした。
ドスード・ニッサンモータースポーツは、ドスード設立50周年の今年、昨年の8位よりもよい成績を狙っている。「一年を通して多くを学んだ」とアンドレ・ドスード。「新型テラノの信頼性は証明されているし、すばらしいチーム体制だ。これまでで一番の結果を出せる自信がある。」