ベース車両の諸元を比較した表で見れば分かることだが、そのひとつはボディの大きさ。大きなボディは必然的に重く、同じ技術的レベルで軽量化してもスタートでのハンデイは、そのまま残ってしまうことになる。バネ上が重いということは、あらゆる面で運動性能上不利になる。また、当然前面投影面積も大きく、これは空気抵抗係数を同じレベルまで良くしても、ドラッグとしては差が残り、加速性能、最高速で負けてしまう。
| スカイラインGT-R | トヨタ スープラ | ホンダ NSX | |
| 全幅(mm) | 1785 | 1810 | 1810 |
| 全高(mm) | 1360 | 1275 | 1170 |
| 車両重量(kg) | 1530 | 1430 | 1350 |
| FR重量配分(%) | 56.8 | 53.1 | 41.5 |
2000年版 自動車諸元表引用
ふたつ目は、フロントに重量の重い直6エンジンを搭載するというレイアウト。重量配分がフロントヘビーで、かつヨー慣性が大きく運動性能上、明らかに不利。GT-Rベースのレースカー開発は、このふたつのハンディを如何にリカバリーするかということに尽きる。
従来の開発では、この運動性能上のハンディはどうしようもない物として、例えば給油速度を上げピットワークの時間を削る等、別の方法でのリカバリーを進めてきが、00仕様の開発は「速さ」をコンセプトにし、このハンディそのものに真正面からチャレンジすることにした。現実的にはボディフォルムは規則上の制約でほとんど手を入れられないため、前面投影面積のハンディはやむをえない。したがって重量と重量配分の改善を最大限に進めることで取り組むことにした。
また、ベース車両の如何にかかわらず、レース車両として最も重要な課題は、重心高を可能な限り下げるということ。そこで、重心高を含めた以下3点を、性能向上のポイントとした。
- 最大限の軽量化
- 最大限の前後重量配分の改善
- 最大限の低重心化
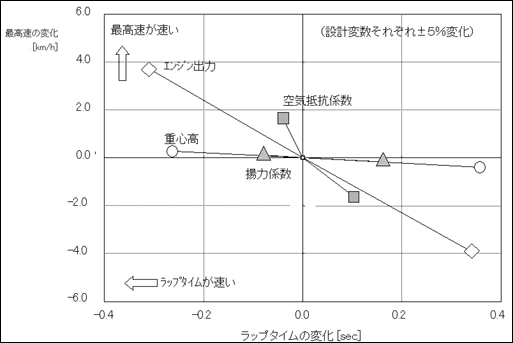 |
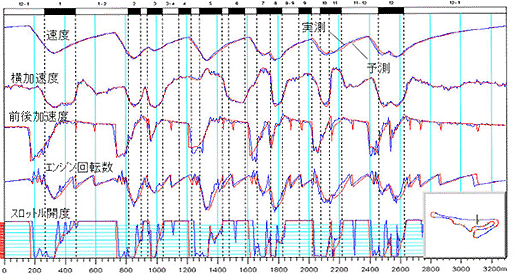 |
まず、目標を速さのトレンドに、変動要素である車両規則、技術動向等を加味して決める。00仕様の目標としては、先のトレンドにエンジン出力、空力性能面での規則変更を加味し、富士スピードウェイのレースで1分25秒中盤を設定しています。
次にこの目標のタイムを達成するために、各性能要件に定量的に割り付けていく。ここで非常に有効なツールが、ラップタイムシミュレーションとなる。NISMOのラップタイムシミュレーションでの検討例を示すが、各々の感度、実現性を評価しながら、各性能要件に割り付けていく。ラップタイムシミュレーションの精度は、開発された車両の性能に非常に大きく影響する。NISMOのシミュレーション精度は、予測結果と実測の比較例。ずれは1%以内と非常に良好な精度であり、これが予測型の開発を可能にしているといえるだろう。
この結果、軽量化については1クラス下の重量クラスをカバーできるように50kg以上(車両規則で同一の性能になるように車両重量とエンジン吸気を制限するエアリストクターの組み合わせが決められており、参加者が組み合わせを選べる様になっている。この車両重量の設定が50kgごと)、重量配分については1%以上の改善、重心高については5%以上の低下を定量的な目標とすることにした。
性能要件ごとに目標が決まれば、次はそれを実際の設計に反映させていく。まずは、軽量化と重量配分の改善。一般的に開発の効率を考え、フロントに搭載される重量物の軽量化に集中的に取り組むのだが、00仕様では最大限というキーワードのもと効率を無視し、車両を構成する全てのユニット、部品(2000点以上)について軽量化を検討することにした。そこで生み出した余裕を全てリヤアクスル上に置くことで重量配分も最大限に改善されることになる。
|
|
|